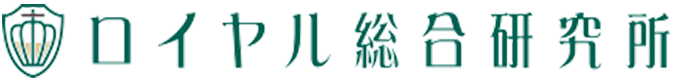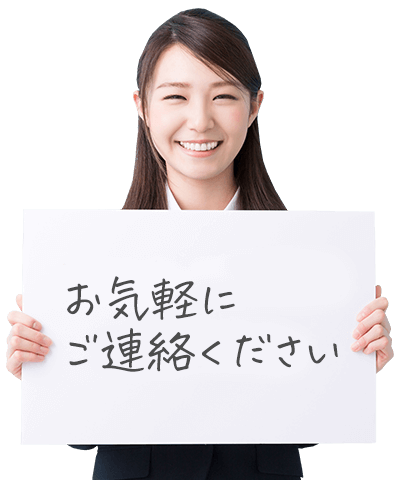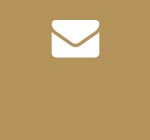| 法改正 | 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き厳格化 |
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが次のように厳格化されます。 【令和7年3月まで】 【令和7年4月より】 ②と③の書類は、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであるか確認するために追加されました。 育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に1歳6か月または2歳まで延長受給できます。 |
| 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります | ||
| 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について(留意点) | ||
|
法改正
|
【令和7年度】任意継続被保険者の標準報酬月額上限 |
令和7年度の協会けんぽ任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円となります(令和6年度は30万円)。上限額は、②の方法で毎年見直されています。 【任意継続加入制度について】 ・資格喪失日(退職日の翌日等)の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること 保険料は、次のいずれか少ない額を標準報酬月額として決定されます。 退職後にいずれの保険に加入するかは退職者本人の判断によります。標準報酬月額の上限は、その判断材料のひとつとなりますので、必要に応じて退職者へご案内ください。 |
| 退職後の健康保険のご案内 | ||
|
法改正 |
「両立支援等助成金」2コースの改定 |
令和6(2024年)12月17日より両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」と「出生時両立支援コース」が拡充されました。 ◆出生時両立支援コース ◆育休中等業務代替支援コース これらの拡充は、男性の育児休業取得をより促進し、かつ育休等取得中の業務代替をサポートすることで業務体制の維持を支援するために行われるものです。令和7年は、改正育児・介護休業法の施行も控え、一層、仕事と育児の両立を実現する環境を整える努力が企業に求められています。本助成金の活用にご興味がございましたら、担当までご相談ください。 |
| 令和6年度12月の変更点(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充) | ||
|
法改正
|
くるみん等の認定基準改正 |
時限法「次世代育成支援対策推進法」の有効期限が10年間延長されました。それに伴い、令和7(2025)年4月より、くるみん認定等の認定基準等が改正されます。 「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律であり、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。主な改正内容は次のとおりです。 ①行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け ②くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準見直し くるみん等の認定は、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。関連法令の改正に合わせて、認定のハードルは上がりますが、仕事と子育ての両立可能な社会の実現に向けて、積極的な取り組みが期待されています。 |
| くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます | ||
|
法改正
|
技能実習 運用要領一部改正 |
技能実習制度運用要領が令和6(2024)年11月1日に改正されました。そのなかで、やむを得ない事情がある場合の転籍の改善が図られています。 【背景】 【改善のポイント】 今回の運用要領の改正では、この他、本人が所有する携帯電話等の私物や健康保険証(マイナ保険証)を取り上げる行為の禁止が明記されました。 技能実習制度は育成就労制度に移行しますが、人権侵害防止策は一層強化されることが想定されます。人権保護はもちろん、外国人労働者に選ばれる企業を目指す意識改革が求められています。 |
| やむを得ない事情がある場合の転籍の運用を改善しました | ||
|
時事
|
令和6年「高年齢者雇用状況等報告」結果公表 |
厚生労働省が、令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を取りまとめ、公表しました。高年齢者の雇用等に関する措置について、令和6年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。 現在、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが、すべての企業に義務として課されています。 集計結果の主なポイントは次のとおりです。 ・70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況:実施済みの企業31.9%(中小企業32.4%、大企業25.5%) 中小企業で就業確保措置の実施や定年制の延長が進んでいることが分かります。中小企業ほど人手不足の影響を受けていることが背景にあると考えられます。本調査とは別に、労災事故において60歳以上の労働者が占める割合の増加が課題として上がっていますので、高齢者の継続雇用/就業機会の確保の措置を講ずる際には、労災事故防止対策も合わせて検討することも重要です。 |
|
|
|