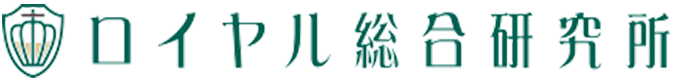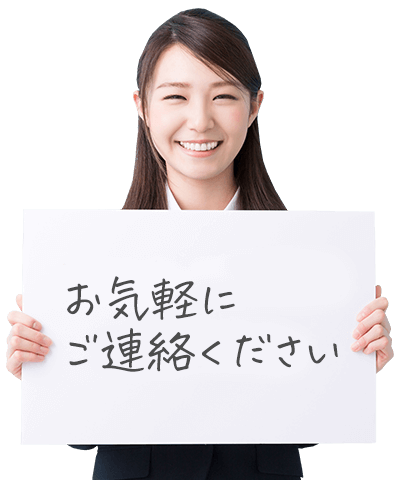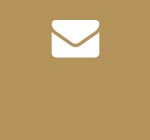| 法改正 | 令和7年度協会けんぽ健康保険料率 |
・令和7年度の協会けんぽ健康保険料率及び介護保険料率が公表されました。今年は、大分県を除く都道府県において、保険料率が改定されます。全国平均は10%、最も高い佐賀県と最も低い沖縄県の差は、1.34%になっています。なお、静岡県の保険料率は、9.80%(前年9.85%)です。 ・介護保険料率は、全国一律で1.59%(前年1.6%)です。 4月の給与計算を前に変更をご確認ください。 |
|
法改正 |
在職老齢年金の支給停止調整額の改定 |
・令和7年度の年金額の改定が行われました。 ・在職老齢年金は、働きながら年金を受け取ることができる制度で、賃金(賞与込み)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合に年金の一部または全額を支給停止する仕組みです。 60歳超で老齢厚生年金受給中の社員の処遇を決定する際に当制度を参考にしている場合は、変更にご注意ください。 【その他の改定内容】 |
| 令和7年度の年金額改定についてお知らせします | ||
|
法改正
|
育児時短就業給付金の創設 |
令和7年4月から育児時短就業給付金が創設されます。 ◆対象 ◆支給期間 ◆支給額 ◆経過措置 令和7年4月からは、2月にご案内した「出生後休業支援給付金」の制度もスタートします。また、改正育児・介護休業法の一部も施行されます。4月は育児・介護関連の多くの変更点が控えていますので、今一度対応に漏れがないか、ご確認ください。 |
| 「育児時短就業給付金」を創設します | ||
| 育児時短就業給付の内容と支給申請手続 | ||
| 育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説 | ||
|
法改正
|
雇用保険の基本手当(失業給付)に係る給付制限の変更 |
令和7年4月より基本手当(失業給付)の給付制限が次のように変更されます。 ※給付制限とは、雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合において、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、基本手当の給付が制限される期間です。 (1)原則2か月から1か月に緩和(ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月) (2)令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限解除 (2)については、次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた、 または離職日以後に受けている場合に対象となります。 ① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 ② 公共職業訓練等 国は、リ・スキリングと成長産業への労働力移動に力を入れており、給付制限の緩和は、労働者の失業中の生活に対する不安や負担を軽減し、安心してキャリアアップや再就職活動を行えるようにするためのものです。企業側は、雇用の維持と人材確保のため、雇用の流動化に備えた対策が求められています。 |
| 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | ||
|
時事
|
【リーフレット】職務給の導入に向けて |
厚生労働省が職務給の導入促進のため、リーフレットと手引きを公開しました。 本手引きでは、企業が職務給の導入を検討するにあたって、職務給がどのような導入状況にあるのかを知ることが必要として、次の項目に分けて導入状況が紹介されています。 1.職務給を導入している企業の特徴 働き方の多様化を背景に、また年功序列からの脱却や人材の確保と定着への対策のひとつとして、職務給制度が注目されています。貴社の賃金制度の見直しを検討されている場合は、ひとつの案としてご参考ください。また、ロイヤル総合研究所では、賃金制度のコンサルティングも行っておりますので、是非ご相談ください。 |
| 職務給の導入に向けた手引き | ||
|
時事
|
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ |
厚生労働省は、2024年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ、公表しました。この届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、事業主にハローワークへの届出が義務付けられているものです。 届出状況のポイントは次のとおりです。 1.労働者数の状況 2.雇用事業所数の状況 3.国籍別の状況 4.在留資格別の状況 外国人労働者の在留資格別の状況において、「身分に基づく在留資格」を抜いて「専門的・技術的分野の在留資格」が初めて最も多くなった点が注目されています。雇用環境における外国人労働者の役割が、年々大きくなっていることがうかがえます。 |