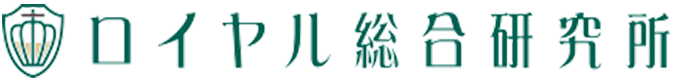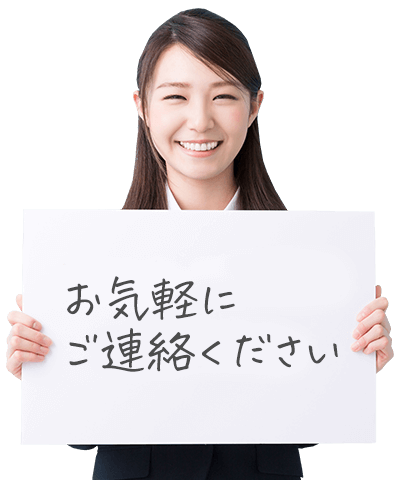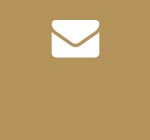| 法改正 | 現物給与価額改正 |
・令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されました。
・労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算して報酬に合算し、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めます。
・今回、食事の価額は、40都道府県において改正されました(静岡県の価額は改正ありません)。
現物給与価額の変更は、固定的賃金の変動に該当するため、随時改定や算定基礎届の際はご注意ください。 |
| 令和6年4月から現物給与の価額が改正されます。 | ||
|
法改正 |
育児・介護休業法等改正(令和7年) |
厚生労働省が育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要を公表しました。
少子高齢化社会の進行を背景に、これまでも育児・介護休業法は改正を重ねてきました。今回の改正の概要は次の通りです。
①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
②育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
施行日は令和7年4月1日(一部除く)です。
|
| 育児・介護休業法等法律案の概要 | ||
|
法改正 |
職業安定業務統計令和7年度適用分から新分類に |
・職業安定業務統計に用いる「厚生労働省編職業分類」の改定に伴い、令和7年度適用分から、職業安定業務統計を用いた一般賃金は、改定後の職業分類に基づき公表されることになりました。
■大分類項目の見直し(11項目→ 15項目)
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合は、派遣労働者の賃金を「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下、一般賃金)の額以上」とすることが義務付けられています。職業安定業務統計の一般賃金を選択する場合は、適切な職業分類を選択するよう、改めてご確認ください。
|
| 職業安定業務統計令和7年度適用分から新分類を使用します | ||
| 職業分類表 | ||
|
法改正 |
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて |
出入国在留管理庁は2月、在留資格に関連するガイドラインと運用指針を改正しました。
令和5年6月、専修学校の専門課程の学科のうち、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設されました。これを受けて、今後は、この認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した学生が、在留資格を「留学」から高度人材に相当する「技術・人文知識・国際業務」に変更する際、専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断するとしています。
これまで、専修学校の卒業者は、大学卒業者と比較して、専攻科目と業務の関連性が厳しく問われてきました。今後は、一部の専修学校卒業者については、従事できる業務の幅が、外国人採用を進めている企業については、採用対象の範囲が広がることになります。
|
| 外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて | ||
| 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | ||
|
法改正 |
特定技能 対象分野の追加 |
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、次の様に、対象分野と業務が追加・再編されました。
・新分野:「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」
令和6年4月から向こう5年間の各分野の受入れ見込数の再設定も行われています。総枠は82万人(5年間)となりました。分野別の見込数は、分野別運用方針でご確認いただけます。
さまざまな産業で人手不足が深刻化するなか、特定技能の在留資格による外国人労働者は、即戦力として期待されています。外国人労働者の採用をご検討の場合は、弊所までご相談ください。
|
| 基本方針および分野別運用方針 | ||
|
法改正 |
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 |
内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定され、公表されています。
指針策定の背景として、急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、日本の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要、としています。
本指針では、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動が12の行動指針として取りまとめられています。また、それぞれの行動指針に該当する労務費の適切な転嫁に向けた取組事例や、受注者が用いている根拠資料や取組内容が取り上げらえています。
価格交渉の際には、労務費の適正な転嫁を実現するために、本指針をご参考ください。
|
| 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について | ||
|
時事
|
令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン |
厚生労働省では、新入学の時期に合わせて、4月1日から7月31日まで、全国の大学生等を対象として、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
学生たちに次の事項を重点的に呼びかけるとしています。
採用する企業側も、上記事項について適切に対応しているか、この機会にご確認ください。
|
| 事業主の皆さんへ アルバイトの労働条件を確かめよう! | ||
| 時事 | 派遣先向けリーフレット公開 |
厚生労働省が派遣先向けのリーフレットを新規に公開しました。
①「同一労働同一賃金」の実現:「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の解説
物価が上昇するなかで賃上げを行うため、労務費の適切な転嫁による取引が、派遣業界にも求められています。派遣先に期待されている内容を本リーフレットでご確認ください。
|
| 派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています | ||
|
時事 |
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」 |
経済産業省が、「ビジネスケアラー」を取り巻く諸課題の対応として、企業による仕事と介護の両立支援の取り組みを促すため、ガイドラインを策定し、公表しました。
・背景:超高齢社会及び生産年齢人口の減少、介護に起因した労働総量や生産性の減少による労働損失
さらに、企業が取り組むべき事項をステップを設けて解説しています。
少子高齢化が進み、労働力人口の不足が加速するとともに、ビジネスケアラーが確実に増えていきます。企業の持続的成長のため、将来を見据えた両立支援策の検討にご参考ください。
|
| 仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン |