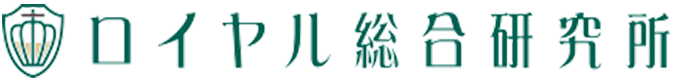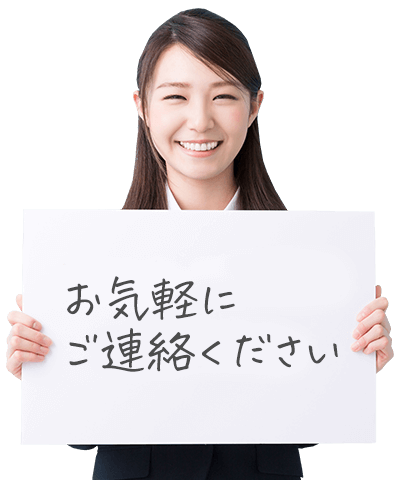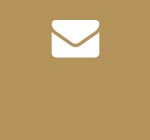企業型確定拠出年金制度(企業型DC)は、老後資産形成の有力な手段として多くの企業で導入が進んでいます。企業が従業員の将来の資産を計画的に積み立てるための制度です。企業が拠出した掛金は全額を福利厚生費として損金算入できます。
この制度の会計上における仕組みを理解できれば、法人税を正確に計算することができます。税務対応を複雑化せず、進めていくためにも会計処理の基礎をしっかり抑えておきましょう
目次
企業型確定拠出年金制度における掛金拠出
企業型DCは、主に企業が拠出する掛金を元にもとに従業員が自らが投資信託を中心に運用する制度です。将来受け取る年金は、この運用成績に応じて決まります。運用リスクは従業員自身が負う一方、運用結果次第で資産を効率的に増やせる可能性があります。
「確定拠出」とは、企業が拠出する掛金の額があらかじめ決まっていることを意味します。企業としては掛金を拠出した時点で財務的な責任を果たしたことになります。
なお、拠出する掛金方法は、全ての加入者(従業員)に対して同一の掛金額を設定する「定額方式」と、給与額に基づき、一定の比率を乗じた額の掛金を算出する「定率方式」があります。この定率方式は従業員の職位や役職などの基準を元に、段階的な掛金の増減を行う場合もあります。在籍する従業員数や財務状況に応じて柔軟に運用していくことも可能です。
企業型確定拠出年金の会計処理と仕訳の基本
企業型DCは、加入者の掛金を拠出した場合、全額を福利厚生費として経費計上できるのが特徴です。
企業の財務管理を円滑に行うためには、適切な会計処理を行うことが必要です。そのためにどのような仕訳をすればよいのか解説します。
1)掛け金を拠出した時の仕訳
掛金を仕訳する際、まず企業が拠出する額面を具体例で仕訳をみていきます。
例)当期の掛金が20,000円
| 借方 | 貸方 |
| 法定福利費:20,000円 | 預貯金:20,000円 |
ポイントは勘定科目を「福利厚生費」とするとことです。掛金が従業員の福利厚生の一環として適切に処理されていることを明確にします(「退職給付費用」でも可能)。掛金を正しく仕訳することで企業の責任を果たし、税務上も整合性を保つことができます。
2)企業型確定拠出年金制度を選択制とした時の給与の関係
企業型DCを従業員が任意で加入する「選択制」という制度設計で導入した場合、従業員が各自で掛金を拠出するかを判断できます。具体例を挙げてみていきます。
例)給料が25万円・生涯設計手当(ライフプラン手当)として3万円を支給している従業員に給与を支払った場合
| 借方 | 貸方 |
|
給与:250,000円 福利厚生費:30,000円 |
預貯金:280,000円 |
給与は掛金を除いた金額になります。掛金はそもそも給与ではないため、給与額には含めません。
企業型確定拠出年金制度の掛金「生涯設計手当(ライフプラン手当)」は、給与と別に定める「生涯設計手当規程」に基づき支給します。退職金と同じ扱いをするため、生涯設計手当も給与の一部とはみなしません。
3)手数料の経理処理
掛金拠出時は手数料が発生することがあります。手数料は支払手数料の勘定科目で下記のように処理をします。
手数料も正確な処理を行うことで経費として認識でき、法人税の計算にも正確に反映されますので確実に実施しましょう。
例)支払手数料が2,000円だった場合
| 借方 | 貸方 |
| 支払手数料:2,000円 | 預貯金:2,000円 |
企業として取り組むことの意義とポイント
企業型DCは従業員の老後不安を軽減する企業年金制度として近年、中小企業の間で注目されています。福利厚生の一環として導入することができ、企業負担が少なく導入できるため、中小企業(5名~30名規模)での増えており、今後企業にとって強力なインフラにもなり得る制度です。
導入に際しては企業として様々な事前準備を整える必要があります。具体的に見ていきましょう。
1)導入時、導入後に大切なこと
企業型DCを企業で運用する際、適切な手続きと税務への対応が求められます。制度導入にあたり、就業規則の改定、従業員への投資教育を行う必要があります。
企業型DCを導入する第一の目的は従業員の満足度を向上させ、人材確保や人材定着につなげることです。そのための福利厚生制度として導入するために就業規則の改定が必要となります。
また導入後、制度を機能させていくためには従業員が制度のメリットや仕組みを理解することが肝心です。制度の導入時だけでなく導入後も、継続的に投資教育を行う必要があります。
2)税務処理への正しい理解
また掛金拠出時の税務処理への正しい理解も必須です。掛金拠出の方法は2種類あり、「企業が掛金を拠出する」「従業員が拠出する」となっています。それぞれ仕訳方法が異なります。今回は「従業員が拠出する」パターンで解説しました。
正しく費用計上と税務対応を行うことができるかどうかが鍵となります。制度の仕組みを理解することは、そこまで難しいことではありません。税務対応が正確であれば、その後の申告業務もスムーズです。税務調査の際も安心です。また何より税金や社会保険料を正確に納付するためにも正しい税務対応の理解は欠かせません。
経理業務では日常的な仕訳や帳簿管理を正確に行うことが求められます。企業型DCを導入時は、事業主だけでなく経理担当者にも正しい仕訳方法を理解してもらう必要もあるでしょう。
最後に
企業型DCで拠出した掛金は福利厚生費として損金算入します。企業型DCを任意加入の選択制で導入した際は給与と掛金を分けて仕訳をします。
正しく福利厚生費を計上して企業が納める税金を最適化していきましょう。
企業型DCは従業員の老後の不安を軽減し、将来の資産形成をするサポートをするものとして重要な役割を果たします。従業員が自分の価値観やリスク許容度に合わせて運用商品を選択し、非課税で運用できるため、将来の年金不安を解消する手助けとなるでしょう。
企業型DCは労使双方にとってのメリットも多く、労働環境の整備に寄与する制度として、大変優れた国の制度です。
導入検討の際は専門家の意見を参考にし、自社の状況に合った制度設計を行うことをお勧めします。